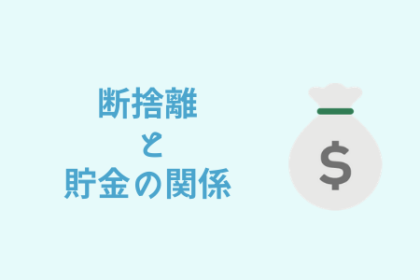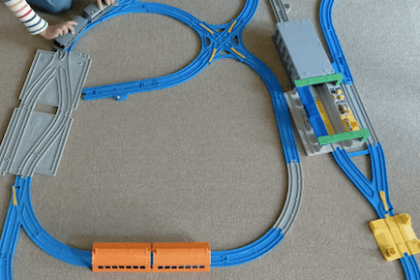勝間和代の断捨離本を読んだら、長年の悪習慣を断ち切れた。私に起こった2つの変化

家が散らかりはじめたので、勝間和代さんの『2週間で人生を取り戻す! 勝間式 汚部屋脱出プログラム』を読んでみました。
やっぱり人は、自分で気づいて、しっかり腹落ちしないと、行動できないのです。
これは本書に書いてあった言葉です。
そう、わかっちゃいるけどやめられない。・・・ってこと、たくさんあります。
理解できるし、そして周りから指摘もされる。だけどやっぱり腹の底から自分が納得しなければ、ダメだダメだと思っていても何も変われないんですよね。
しかしこの本によって私は、「しっかり腹落ちしたから行動できた」ことがありました。
そしてその後、私の長年の2つの悪習慣が終わりを告げたのです。
1. ふだん使っているものは、ボロボロなことに気づく
服でもバッグでも、ふだんよく使っているものってあると思います。
私はそれが顕著で、ズボンでもTシャツでも靴でも、気に入っていたり使いやすいものはずっと使って「着倒す」「使い倒す」タイプです。
断捨離を始めてみて、まず驚いたのが、「いかに、ふだんよく使っているものがボロボロか」という事実です。つまり、私たちは、
・愛用している2割のものはボロボロ
・使わない8割のものは新品のままスペース占有
という状況に置かれていることが多いのです。
この
「いかに、ふだんよく使っているものがボロボロか」という事実です。
が、ガーン!と響いたのです。
私の場合、使わないものはどんどん捨ててしまいます。一方で使うものは使いまくる。そして穴が開いたり、破けたりなど致命傷を負わない限り、断捨離対象に入らなかったのです。
おまけに、他人が着ているボロはわかるが、自分が着ているボロはよくわからない体質。
周囲からも指摘されていました。「ボロボロだから新しいのを買ったほうがいい」「使いすぎてて生地が傷んでいるからみすぼらしいよ」と。
でも自分のこととなると、さっぱりわからないのです。ふだん着ている服だと「どこがボロボロ?」と心の底から思ってしまうのです。
本書は、勝間さんが断捨離をする過程とともに書かれているからでしょうか。
まずは、使っていないものを処分し、よく使っているもの、例えば、財布と日常使いのカバンなどを、新しいものに買い替えました。
どちらも恥ずかしいくらいボロボロにすり切れていました。
読んでいたら、
「ああ、私の物も恥ずかしいくらいにボロボロだ」、と急にスッと理解できたのです。
思い起こせば、夏に着ているTシャツももう7年くらい着ているし、リュックだって10年以上使ってる。会社用バッグは12年・・・。下着ですら6〜7年使っているものが多くて愕然としました。
食べ物に賞味期限があるように、服にも確実に期限があります。ある一定の期間をこえると、気持ちよさやパワーはなくなってしまうんですよね。
わかっていたはずなのに、使いまくってるものに対してはそんな考えがすっぽり抜け落ちていました。
ふだん使っている服や物を改めて新鮮な目で見れるようになり、そしていくつかは新しく買い直すきっかけになりました。
とにかく、やることはひとつで、
・活躍しているものたちには、もっとお金とスペースを配分し
・活躍出来なかったものたちは、捨てるか、活躍先を探す
という当たり前のことです。
ほんと、ボロボロでした、私の持ち物。急に目が開かれた感じ。真実がようやく見えましたよ 笑。
きれいなものは、やっぱり気持ちいいですね。
周囲の人に不快感を与えることもないし、何より自分が気持ちいいと、大げさかもですが生きていて清々しいです。
2. シンクに洗い物をためなくなった
さらに、私に起こった2つ目の出来事は「シンクに洗い物をためなくなった」ことです。
私は食器を洗うのがとても嫌いで、どうしてもためてしまう。そしてたまった食器を見ながら気分がちょっと落ちる・・そんな日常を送っていました。
でも、食器自体を少なくすることで「ためすぎ」は回避はしていました。
でもやっぱりためているのには変わりがない。
しかし
私たちは掃除でも洗濯でも買い物でも、なんとなく、「まとめてやるほうが、効率的で経済的だ」と思いこんでいるところです。実は、これは、大きな間違いです。
この文章以降を読んだら、ぴったり食器をためることがなくなったのです。
私は、若い頃にコンピュータのプログラミングをしていたのですが、その時に
・バッチ処理
・逐次処理
という二つの処理方法を習いました。
バッチ処理とは、何かをためて、一気にまとめて処理をするもの。一方、逐次処理は、リアルタイム処理ともいい、その都度行う処理の仕方です。
(中略)
実は当たり前ですが、逐次処理のほうが、よっぽど物事は全てがスムーズに進むのです。
これは、すべての物事の仕組みとしてとらえる「システム論」でもいえることです。
(中略)
洗濯や皿洗いも「洗濯機や食洗機1回分の分量がたまるまでまで待つ」のをやめ、気がついた時に、少量で回すようにしました。すると時間もかからないし、洗濯物を干すのもあっという間です。
この中略した部分がもしかしたら私が腹落ちするのに重要な部分だったのかもしれませんが、とにかく論理的な切り口から話が展開されるからでしょうか、完全に腹落ちしました。
実は、ありとあらゆるものがたまらなければ大した手間ではないことに驚きます。
やってみると本当にそうで、大した手間じゃないし、きれいをキープできることで気持ちいいのです。食器がたまったシンクを見ることがないから、ストレスがないのです。
実は、この「まとめてやらずに平準化する」というのは、投資や経営にも通じる普遍的なルールです。
これまでシンクに食器をためていたし、さらにさあやるか、と食器を洗い始めてもなぜか最後の3個くらいは洗わずにそのまま置いておく謎の悪習慣までもがありました。
ダメだと思ってもどうしてもしちゃう。だからこそプチストレスだったんですね。
なので、この妙なためてしまうクセがなくなったことで、とっても!解放された気分です。
ストレスはできるだけ除いて、気持ちよく生きていきたい。常々思っていることなので、また一つストレスがなくなって気持ちいい限りです。
経済評論家らしい断捨離本
ロジカルさが随所にあらわれていて、従来の断捨離本とは趣の違う本でした。
ご紹介した2つのこと以外にも心に残る言葉はいくつかありましたので、ピックアップしておきます。
・「目標」を達成するには、努力や意志の力ではなく、「仕組み」を作ることが大事
・使用頻度のわりにスペースを食うものは捨てる、ということがキモになる
勝間さんが買うものをどうやってセレクトするか?でたどり着いた結論は▼
ものは使用頻度と占有スペースで選ぶ
ということです。
ちょっといいな、とか、安くてお得、と思ったとしても、それをどのくらいの使用頻度で使うのか、部屋の中でどのくらいのスペースを食うのか、まず考えてみましょう。価格が安くても頻度が低ければ高いもにになりますし、大きいとスペースコストが高くなります。そう考えると、価格はあまり関係ないということが分かるでしょう
勝間さんは断捨離をやってみて、自身で感じた効果について以下のように語っています。
断捨離の効果については、短期間で現れる現世利益的なものから、人生をジワジワ変えていくような深淵なものまで、本当に想像以上のものがありました。
やせたり、恋人ができたり・・・などなど断捨離効果でよく言われることがやはり起きたそうで、その分析についても興味深かったです。
世の中には情報も本もたくさんありますけど、行動を促されたり、変化が訪れる本はさほどありません。
本書の後半部分は生活スタイルの違いから眺める程度になりましたが、前半部分だけで長年の悪習慣を断ち切れたので、私にとっては大きな1冊となりました。
【あわせて読みたい】